『コラム』

- ニセコインターナショナルクリニック
- 2025/09/11
運動する成長期の子どもの栄養を見直す
今回は運動をする成長期の子どもの栄養について書きます。最近は、子どもたちも大人と同様に日常的に運動不足で、肥満の問題が増えているという記事を多く見かけますが、その一方で、厳し過ぎる環境で運動をしている子どもたちもいます。
昔と比べ、子どもたちの競技のレベルが上がってきているにも関わらず、適切な運動負荷や栄養のとり方については、昔のままな部分もあるように感じます。
コンディションが悪いと、頑張っても良い結果が出せなかったりケガをしたりするのですが、子どもたちは体の不調を押してでも一生懸命に練習をしようとしています。こういった患者さんを見る度、この状況をどうにかしなければと思わされます。
参考資料はこちら
「Youth Athlete Development and Nutrition」
成長期の子どもと大人との大きな違い
一生使う「身体づくり」の時期
大人のアスリートは、「今」の体のコンディション維持やより良いパフォーマンスがメインの目的になります。一方で子どもは、運動をする以前にまず自分が「将来」生涯使うことになる体を作らなければなりません。それだけで、すでにかなりのカロリーや栄養が必須です。
体が「急激に」成長する
成長のスパートは急激にやってくるので、大人のように「去年までも〇〇だったから、きっと今年も〇〇〇」と考えるのではなく、今の体と運動の状況に合わせて必要な栄養を調整していく必要があります。
成長期の子どものサイズの変化は想像以上のスピードです。除脂肪量(体から脂肪を除いた部分=筋肉、骨、内臓など)は成長のピークで、女子は〜2.3g/日、男子は〜3.8g/日増えるというデータがあり、これは思春期前の子どもの3倍だそうです。海外のデータですが、身長の成長スパート(背が伸びるスピードが人生で一番速くなる時期)は、男子は11.4cm/年で13歳、女子は8.7cm/年で12歳と、ある研究では報告されています。(Philippaertsら2006年、Yagueら1998年)
短いスパンで必要な栄養の量が変わっていくため、それに合わせてこまめに調整していく必要があるということです。
ホルモンなど体の中での変化や「思考」が変わる
小さいときは最も影響を与えるのは家族だったはずですが、思春期になると友人や部活の監督などからより強く影響を受けるようになります。他人の目を気にするようになり、自分の体型も気になるようになります。摂食障害のきっかけにもなるので、成長期(=思春期)は、正しい教育が重要な時期です。
身体活動の種類が多い
大人の日常生活は、身体活動の種類がそれほど複雑ではありません。しかし、子どもたちは、学校の体育、友人との外遊び、部活やスポーツクラブといった課外活動など種類の違う身体活動を日々こなしています。そのため、大人のスポーツと比べると、必要なエネルギー計算も複雑になります。これは主に運動のエネルギー源である炭水化物に関わります。
カロリーが不足すると…
身体づくりのためのタンパク質が本来の役割を果たせない
身体活動に必要なエネルギー源(主に炭水化物)が不足すると、その代替エネルギーとして肝臓に蓄えられたグリコーゲンや体内のタンパク質が使われてしまいます。これは本来の役割である「筋肉などの体を作ること」に回されるタンパク質の量が減るということです。
骨形成に悪影響
大人の女性アスリートでもカロリーが足りなくなると、月経が止まります。女性ホルモンであるエストロゲンの分泌が下がるからです。エストロゲンが不足すると、骨づくりのバランスは「壊す>作る」になります。閉経後の女性が骨粗鬆症になりやすい理由と同じことです。
20歳くらいまでの骨の形成が将来の骨密度を左右する
骨密度は、20歳頃にピークになりますが、成長期の骨形成がこのピークの高さを大きく左右します。大人になってからの無月経ももちろんよくありませんが、20歳までしか骨密度のピークを上げることができないので、思春期の無月経は他の時期のそれより重要な意味をもつということです。
Food Firstで先手を打つ
以上の理由から栄養不足はできるだけ避けたいのです。そのために、成長期の年齢で、進級する、競技レベルが上がるなど、運動負荷が増えることがわかっている場合は、先手を打って食事の量を増やすことが推奨されています。
栄養教育の機会がない現実
ここまで、教科書的なことを書いてきましたが、実際、食事が体の基本だとは言われているものの、大人の競技スポーツでも栄養のサポートは不十分で、子どもアスリートの患者さんで栄養管理までされているのを、私はみたことがありません。
小さくてもできることの積み重ね
からといって食事を工夫しなくていいわけではありません。理想的な食事を達成するのは難しいですが、ちょっとした知識と実践で現状よりは改善できます。
また、食べものを工夫・調整しても体重が増えない場合は、運動量による消費カロリーを減らす必要があります。しかし、実際に練習量を減らせる患者さんは多くありません。
完璧を目指すのではなく、食事でひとつでもやれることを増やす、練習も完全に止めるのではなく時間を短くしたり、強度の弱い練習日をいれるなど、白黒ではなくグレーをうまく取り入れていくことが、健全にスポーツを継続する秘訣だと考えています。
まとめ
・思春期には他の世代と違う成長の特徴がある
・パフォーマンスだけでなく、成長と発達にも栄養が使われる
・成長が急激であり素早い調整が必要
・身体活動が大人より複雑でカロリー計算が難しい
・先を見越して栄養の調整をするように
・できる小さなことの積み重ねが功を奏す
DoctorT
2020年英国UCLでスポーツ医学の修士課程を修了しました。大切だけどあまり知られていないスポーツ医学情報を発信します。
北海道大学卒業。家庭医療専門医。後期研修中、米国での家庭医によるスポーツ診療を知り、興味を持つ。医師12年目に留学を決意。
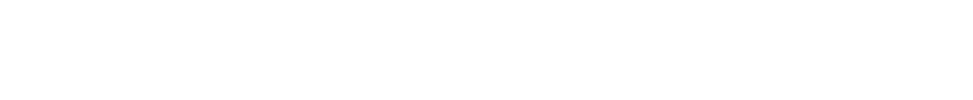
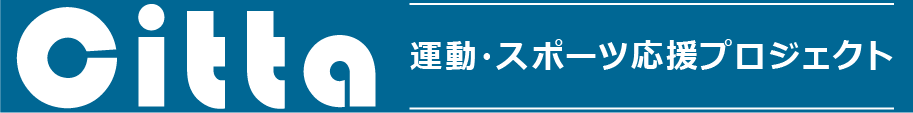
















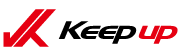



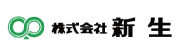





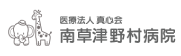
.jpg)
